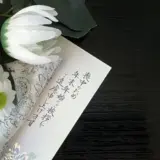神社への質問などで多いのが「厄払いは一人でいくべきなのでしょうか?」というものだそうです。厄払いは本当に誰かと一緒に行ってはいけないのでしょうか?行ってはいけないのであればその理由とは?
また、厄払いのマナーを紹介したいと思います。
厄払いは誰かと一緒に行ってはいけない?
結論から言いますと、厄払いに友人や家族と一緒に行っても問題はありません。同級生などであれば、厄年は同じだと思うので、友人と一緒に日時を合わせて神社で厄払いしてもらうという光景も多く見られます。
また、一人で行くのは心細いということで家族と一緒に来る方もいるでしょう。では、なぜ厄払いは誰かと一緒に行ってはいけないという噂が浮上するのか?次項で詳しく紹介しましょう。
厄払いを誰かと一緒に行ってはいけない理由は?
厄払いを誰かと一緒に行ってはいけないと言われている理由は「神社の厄払いは一緒に行くと厄をもらってしまうから、一人で祈祷した方がいい」という考えからのようです。例えば、家族で神社参拝をし、母親だけ厄払いを受けた場合「払った厄が家族に憑いてしまうのではないか?」という心配があるからだと思われます。
しかし、実際は払った厄が他の人にうつることはありません。厄年の方を厄年から守るのが厄払いなので、払った厄が他人に憑くことはありませんし、そもそも厄年は本人の話なので他の人には関係ないのです。
厄払いマナーを紹介
厄払いに行く際にどんな事に気を付けるべきなのか、また注意するべき点を紹介します。
服装
厄払い、厄除けは古くからの厳粛な風習です。普段着で行く方もいますが、やはりきちんと正装していくのがお祓いを受ける側のマナーになります。男性の場合はスーツにネクタイ、女性の場合はスーツやワンピースでいいでしょう。
一方、ジーパンやサンダル、スリッパなどもダメですし、露出の多い服装なども不謹慎です。神社などによってはHPで服装について注記しているところもあるため、気になる方は確認することをおすすめします。
料金
厄払いの際に渡す祈祷料は「初穂料」と呼ばれます。元来、日本ではその年初めて獲れたお米の稲穂を初穂として、神様に捧げるという風習がありました。現在は、稲穂の代わりとして初穂料としてお金を捧げるのが一般的になっており、料金は5,000円~10,000円が相場になるでしょう。
ただし、神社によって料金が異なるため、事前に問い合わせておくことをおすすめします。包む金額には、忌数字として嫌われている「4」や「9」といった数字が含まれないように注意し、できるだけ新札を用意してください。
料金を入れる袋
料金を入れる袋には、紅白の蝶結び・水引きののし袋または白い封筒を使用しましょう。表書きは、神社の場合であれば「御初穂料」、お寺の場合であれば「お布施」と縦書きにし、下段に厄払いを受ける人の名前を書いてください。
中袋には表面に金額を書き、裏面に住所と名前を記載、中袋がないタイプの場合には、のし袋の裏面に住所と金額を書きます。
祈祷料の渡し方
初穂料は、のし袋を袱紗(ふくさ)に包んで持参し、渡す時には、包んでいた袱紗からのし袋を出します。そして、包んでいた袱紗をたたみ、その上にのし袋の文字が相手向きになるように両手で差し出しましょう。
ごくまれに、のし袋に入れずにお金をそのまま渡す方もいますが、これはマナー違反です。神社によっては、のし袋に入っていなければ受け取ってもらえないケースもあるので注意してください。
お礼参り
お願いしてばかりで、後は知らん顔というのは虫のいい話になり、神仏に対してのマナー違反です。厄払いをしてもらった神社などで、翌年の同時期にお礼参りをするようにしましょう。問い合わせれば、具体的な方法を教えてくれます。
最後に
今回は、厄払いは誰かと一緒に行ってはいけないのか?という疑問と理由、厄払いのマナーを調査しました。厄払いに誰かと一緒に行くことは全く問題ありません。ただし、厄払いの最低限のマナーというものがあるため、この記事を参考にしっかり理解した上で、厄払いをお願いしてくださいね。