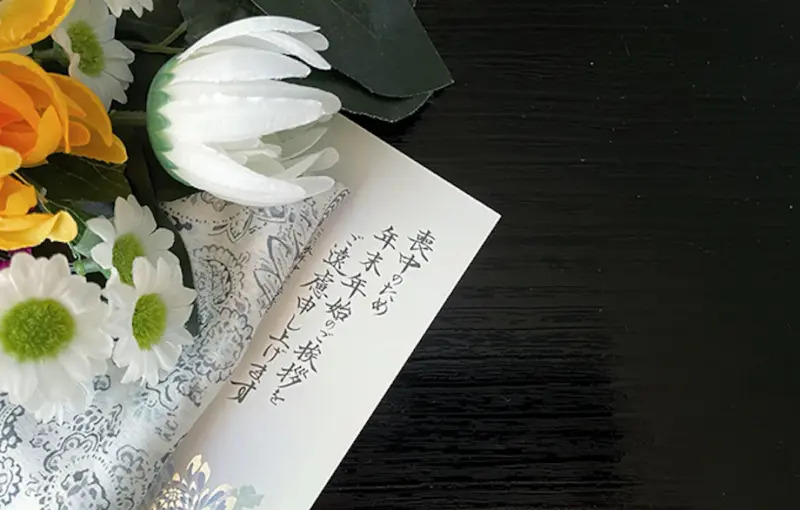近親者が亡くなった場合に、一定の期間、故人を偲び、身を慎む喪中。その期間には控えた方がいいことがいくつかあります。その1つに神社に行ってはいけないというのがありますが、その理由とは何なのでしょうか?
また、忌中との違いや喪中期間に控えることを紹介します。
喪中に神社に行ってはいけない理由は?
結論から言いますと、喪中に神社に行っても問題ありません。喪中に神社に行ってはいけないと言われていた期間は「忌中」のことで、この期間は神道における死が「穢れ(けがれ)」と考えるため、穢れを神社に持ち込んではいけないという理由があるためです。
そのため、忌中があけると喪中であっても神社に行くのは問題ありません。現代ではこの喪中と忌中の区別をせず、喪中とまとめて認識しているため、喪中期間は神社に行ってはいけないという認識になった可能性が高いでしょう。
喪中と忌中の違いは?
喪中に神社に行ってもよいが、忌中は控えた方がいいということがわかりました。では、喪中と忌中の違いは何なのでしょうか?ここではその違いについて解説します。
喪中とは
喪中とは、身内が亡くなった際に、家族や親族が「喪に服す期間」のことを指します。期間中、家族や親族は悲しみを表すために黒い服を着用して、祭祀や宗教儀式に参列することが一般的です。
忌中とは
忌中とは、命日から四十九日法要を迎えるまでの49日間のことです。四十九日法要までは、故人の来世での行く先が決まっていないので、穢れが伝染してしまうと考えられていました。
本来であれば忌中の間、親族が外出を控えるべきとされています。しかし、現代においては、お祝いごとを控える風習だけが残っていることが多いです。
喪中に控えることを紹介!
喪中期間中は厳しく身を慎んで過ごす事がかつては求められていましたが、現在はそこまで厳しくないものの、喪中に控えるべきことや気を付ける事について紹介します。
新年の挨拶や年賀状を出すこと
喪中期間は、お正月祝いは控えてください。新年の挨拶も控え、年賀状も新年を迎えた喜びを伝えるべきものなので、控える代わりに喪中はがきを出すようにしてください。喪中はがきは11月中旬〜12月上旬頃を目安に送付しますが、最近ではSNSの普及ではがきのやり取りが少なくなっているため、LINEなどで済ます方も多いでしょう。
お正月祝い
鏡餅や門松などは、歳神様を迎え入れ、1年を無事に過ごせたことに対する感謝とお祝いをするために飾り付けるものです。そのため、喪中期間は、飾りつけを控えるのがマナーとされています。
中には忌中があけたら飾りつけをしても良いと考える方もいますが、何か特別な事情がない限り、飾らない方が無難でしょう。また、おせち料理を食べることやお屠蘇を飲むこともおめでたいことになるため、控えた方がいいでしょう。
新築物件の購入・リフォーム
新築物件の購入やリフォームはおめでたいこととして捉えられ、喪中にふさわしくないとされています。また、喪中は身を慎む期間であることから、大きな買い物をするのは避けるべきと言われています。
既に契約が済んでおり、キャンセルできない場合を除いては、できるだけ避けた方が良いでしょう。なお、引っ越しに関しては、喪中期間に行っても問題ありません。
結婚や入籍
喪中期間は祝いごとを避けた方がいいという考えから、結婚・入籍も延期すべきというのが一般的です。ただし、結婚や入籍が亡くなった方の強い意向である場合にはそれらが供養になるため、忌中を過ぎれば問題ないという考え方もあります。
最後に
今回は、喪中に神社に行ってはいけない理由や忌中との違い、喪中に控えるべきことを紹介しました。喪中に神社に行くことは問題ないが、忌中は控えるべきということがわかりました。また、同時に喪中や忌中の違いもしっかり解説していますので、ぜひ参考にしてほしいと思います。
喪中に控えるべきことは「おめでたいこと」です。喪中か忌中か控えるべきことがわからないと感じた場合は、「おめでたいことは避ける」と認識しておくのがいいかもしれませんね。